ただ、簡体字である点はどうにかして欲しいと思いますが・・・
少なくとも引用文位は繁体字にして欲しい!

現在までの三国時代&『三国志演義』研究水準を解りやすく紹介し、なおかつ論文目録まで載せてしまうと言う、非常にお得な本です。一冊持っておくとネタ探しに困りません。
ただ、前書きにも書いて有るとおり、ここに載せてある論文がすべてではなく、例えば私のHPに載せてある「曹眞殘碑」については触れていません。朱然墓についても『人民中国』1983-12で紹介されているのを落としています。しかし、これらのデータについては、所収されている論文や単行本などから辿っていけますので、そう問題ではありません。自分で漏れているデータを探すのもおもしろいですよ。
お値段:\3500
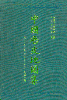
三国時代は三巻に含まれています。カラーで現代の地名と対比して当時の地名を載せていますので、見やすくて便利です。コピーすると区別が付かないので大変ですが・・・
巻末に索引も付いていますが、日本人にとって、簡体字版では非常に引きにくいので、出来るだけ繁体字版を買いましょう(写真はもちろん繁体字版です。)。
漢代の風俗や生活について、考古学の成果を用いてアプローチしてみようとした研究を本に纏めた物です。
三国時代の同様な研究は無いので、後漢の影響が残っているこの時代の習俗を知るためには、必須とも言って良い資料集です。
現物の写真ではなく、写真などからトレースした物が多いのは、発行時代の制約もありますが、もどかしくもあります。
※改訂の話もあったのですが、嘗ての執筆者陣が忙しい為、延び延びになっていたのを、とりあえず再版と言う形で、再び世に送り出したそうです。
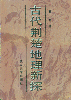
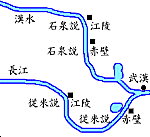 武漢大学の石泉教授の書いた、挑戦的な文献地理学の書物です。
武漢大学の石泉教授の書いた、挑戦的な文献地理学の書物です。なんと「これまでの地名比定は間違っている。私の研究の成果では、南方の地名はもっと北に寄るはずだ! 」というのがその趣旨です。
本来は春秋〜戦国にかけての楚の地名を考察する研究なのですが、その元となったデータの関係で、三国時代も範囲に含まれることになりました。
例えば地図を見てお判りのように、「赤壁」が長江沿い洪湖の畔だとする従来の説に対し、漢水沿いの北緯31.5度〜東経112.5度辺りに比定しています。
学会では無視というよりも、当惑しているのが現状だと思います。東北学院大学の谷口満氏が、紹介文を書いていますので、存在は知っていても、見たこと無い方が多いかもしれません。